【社協だよりいずもvol.156 令和7年2月20日発行号掲載】
出雲市では平成25年度から市民後見人養成研修をスタート。
今年度新たに2人の市民後見人が誕生し、現在3人が活動中です。(令和7年2月現在)
そのみなさんに市民後見人への一歩を踏み出したきっかけや活動を通して感じたことなど、お話をうかがいました。
写真左から
尾添 隆さん :平成25年度研修生。(第1期生)令和5年4月から活動。
松井 幸子さん:令和5年度研修生。(第2期生)令和6年11月から活動。
中谷 昭二さん:令和5年度研修生。(第2期生)令和6年10月から活動。
市民後見人養成研修を受講したきっかけは?
松井:たまたま研修のチラシを見たんです。資格が不要だったので、「わたしでもなれるかも」という気持ちで参加しました。ちょうど退職を考えていたタイミングで、これまでにたくさんの人に助けていただいた分、これからは恩返しができたらと思っていました。
中谷:病院の相談員として30年勤め、4年前に定年退職しました。午前中だけケアマネの仕事をしていますが、生活のメリハリや支柱となるものがあればと考えていました。かっこよく言えば社会貢献できればなと。そんな時に研修の案内を見て。「前職の経験を活かしながらできるかも」とリラックスした気持ちで応募しました。
尾添:知人に誘われた落語の寄席で成年後見制度の話を聞いて、その帰りに「こうしたもんがあるけん受けてみるだわ」と養成研修を勧められたんです。市職員だったのでそれとなく知っていましたが、当時出雲市で取組が始まったばかりで受講者も少なくて…。うまいこと誘導されましたね(笑)。
成年後見制度へのイメージは?
松井:ぼんやりとしたイメージはありました。一人暮らしの親戚のお世話を夫がしていて、公証人役場で遺言書を作成するような、いわゆる終活のサポートも。ご本人から「助かる」と感謝の言葉をいただいていたんですが、急逝されて…。でも、死後のことも話し合っていたので、親戚も納得して色々な手続きを進めることができました。何も決めていなかったら、あたふたしたと思います。みなさんが安心された様子を見て、こういうことが本当に必要なんだと実感する出来事でした。

尾添:後見人といえば縁故者がすることが多いですし、難しいケースは専門職が担うという形だったので、市民後見人の需要があるのかなと思っていました。実際、研修を修了してもしばらく活動はなくて。そこで社協から日常生活自立支援事業の生活支援員にと声がかかり、利用者を受け持ちました。その経験を経て、昨年初めて市民後見人として受任することになりました。
養成研修で印象に残ったことは?
中谷:法律用語が難しかったですね。でも、昨年度は30人程度受講していて、和気あいあいとした雰囲気で学ぶことができてよかったです。弁護士や裁判官など日頃関わらない方の話を聞けて新鮮でした。
松井:ご本人が入所されている施設職員の方から市民後見人をするうえで「分からんことは聞いてね」と話があり、とても心強く、「聞いていいんだ!」と安心しました。
中谷:出雲は成年後見センターもあって、専門職に気軽に聞ける環境にあるので心強いですね。
市民後見人として活動してみてどうですか?
中谷:ケースを受任して、人のお金を預かることに緊張感がありました。そんな経験はしたことがありませんでしたので…
松井:私も人の大切な書類を預かる時は「なにかあってはいけない」と、とても慎重になりました。
中谷:後見人としてどこまですべきか迷うことはあります。まずはコミュニケーションをとるために週1回連絡をしていました。ご本人やご家族との関係性ができるとぐっとやりやすくなりましたね。後見人だと認識してもらえるとうれしかったです。
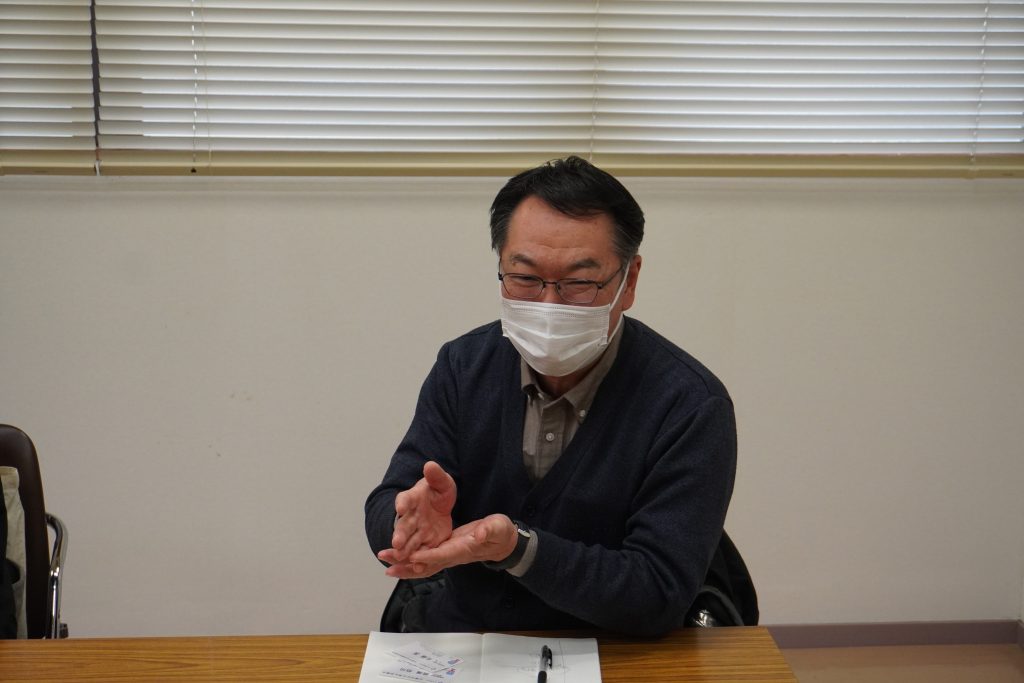
尾添:後見人としての仕事はここまで、という線引きがあっても頼まれると「行ってあげようかな」となりますね(笑)。ご本人がどこまで分かっているのか、満足されているのか、意思疎通の難しさは感じています。
松井:施設職員の方が日頃の様子を教えてくださり、お菓子をおみやげで持って行くととても喜んでいただけました。自分と顔を合わせることを生活の楽しみにしてもらえることがうれしいですね。後見人の役目は金銭管理がメインなのでしょうが、こういう関係づくりも大切にしていきたいです。
中谷:研修でも話のあった「同じ市民目線での関わり」というところが納得できました。金銭管理だけではなく、身上面の支援が大事だと感じています。
被後見人との関わりを通じて感じたことは?

松井:障がいのある方と関わり、忘れていたことに気付かされました。「自分にできることをもっとしていかないと!」と考える機会をいただいています。本当にありがたいです。
中谷:正直、自分も何があるか分からないんだなと感じました。後見人として冷静に見るところと感情移入するところと半々です。縁あって出会わせていただいたので、この経験を大切にしていきたいです。
尾添:受け持ちの方は知的障がいと身体障がいのある方で、ずっと施設での生活をされています。会いに行ってもどの程度理解されているかなと思っていましたが、会うたびに表情に変化があり、通じているものがあるんだと感じました。施設職員の方は長い間関わり、本人のことがよく分かっておられる。関わり続ける時間が力になるんだと思いました。
これからの活動への思い
松井:スタートしたばかりで手探り状態、というのが本音です。でも、事務的なことはもちろん必要ですが、「人と人」であることを大切にして、少しでも安心や楽しみを感じてもらえるように寄り添っていきたいです。
中谷:ご本人の人生がうまくいくように努めたいです。「あの人なら大丈夫!」と信頼感をもってもらえる後見人になっていきたいです。
尾添:ひとくちに成年後見と言ってもケースバイケース。後見人のあり方を問い続け、その人に合ったその人だけの支援を探していきたいです。



